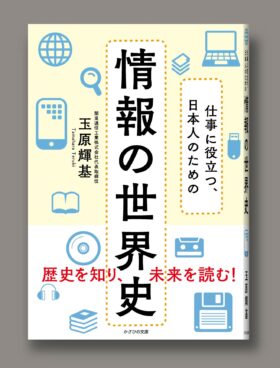『古事記』から『万葉集』を経て、平安の「仮名」につながった
日本で文字が使われるようになったのは、4世紀の終わり頃であると言われています。それ以前は、語部(かたりべ)がさまざまな伝承を後世に引き継いでいました。日本では独自の文字をつくることはなく、朝鮮半島や中国からの渡来人によって漢字がもたらされました。
『古事記』や『日本書紀』には、4世紀後半に在位したとされる応神天皇のときに、百済から王仁という人物が日本に来て、論語巻などを伝えたと記されています。5世紀になると、日本人も漢字を習得するようになったことが、当時の遺文に見られます。西暦471年頃と推定されている、埼玉県の稲荷山古墳から出土した辛亥銘鉄剣(しんがいめいてっけん)には、漢字の音を借りて人名や地名が書かれていて、漢字を表音文字として使用していたことが窺えます。
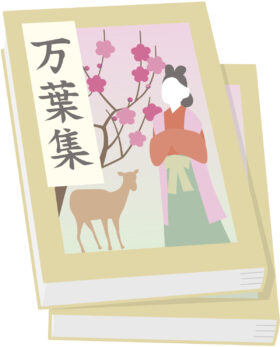
本書の時代区分では中世になりますが、西暦712年に編纂された『古事記』では、漢字の音と訓をうまく使った日本語であらわされています。『古事記』は日本語によるはじめての書物ということになります。表記方法で画期的な書物と言えるのは、8世紀の後半、奈良時代に大伴家持らに編纂された『万葉集』でしょう。4500首の歌が収められている『万葉集』の表記は、漢字の音訓によって日本語を表現した「万葉仮名」が用いられています。これが、次の時代、平安時代に発生する日本固有の文字、「仮名」の源流のひとつになったと言えます。
このコラムの参考文献、弊社代表取締役玉原輝基の2作目『仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史』(かざひの文庫)のリンクはこちら。