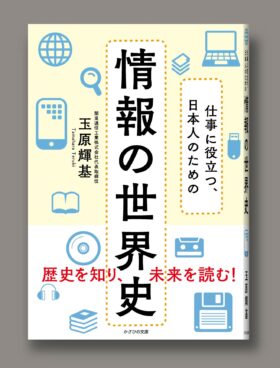活字の数が膨大になる漢字文化圏では活版印刷は定着しにくかった
世界最古の印刷術である木版印刷をはじめたのが中国であることは、前回のコラムでお話しした通りです。
そして、世界三大発明のひとつとして知られる「活版印刷」も、中国がはじまりだったことはご存知でしょうか?
木版印刷は、1枚の板へ版画のように彫刻刀で文字や絵を彫って、版画の表面にインクを塗って、紙などに印刷するものです。これに対して活版印刷は、活字を並べて文章レイアウトをつくり、そこに塗料を塗って印刷する印刷方式です。
活字自体は、かなり早い段階に発明されていたようですが、活字を並べた組版による印刷は、11世紀の北宋王朝における発明家、畢昇(ひつしょう)という人物が知られています。
北宋中期の学者、沈括の『夢渓筆談』によれば、畢昇は1041~1048年頃に、モルタルでつくった活字を用いて印刷をしたそうです。やがて木製の活字が使われるようになり、1221年には木製の活字で科挙受験用の百科事典がつくられたとのことです。
現存する世界最古の活字による印刷物は、温州市の白象塔から発見された北宋崇寧(すうねい)年間(1102~1106年)の印刷の『観無量寿経』と言われています。
この活版印刷は、13世紀末には日本へ伝わり、江戸時代の直前から初期に至って嵯峨本などの活字を用いた印刷物が見られるようになります。

ところが、漢字文化圏では、活字の数が膨大なため、木版印刷が主流であることは変わらず、活版印刷はあまり定着しませんでした。文字数の少ないアルファベットのほうが、活版印刷には向いていたということですね。
このコラムの参考文献、弊社代表取締役玉原輝基の2作目『仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史』(かざひの文庫)のリンクはこちら。