いくらAIが進歩しても、勉強は必要
いまや、ChatGPTを代表とするAIが、世の中を席巻しています。
「AIの進化で、これだけの職業がなくなる」
といったことも、まことしやかに囁かれてもいますね。
ただ、ひとつ注意しなければいけないことがあります。
もし、
「人間はコンピュータやAIには勝てないから、勉強なんてがんばる必要がない。技術なんて身につけなくてもいい」
と考える人がいたら、それは間違いです。
なぜなら、人間はAIによるプロダクトを評価できるだけの知識を持たなければならないからです。
AIのプロダクトの評価は、勉強をしなければできませんよね。
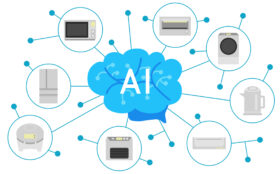
過去のAI研究に関わった立場から思うこと
じつはわたしは、もう40年ほど前、AIの事業に少しだけ携わっていました。
その頃は1980年代に「第2次AIブーム」があり、「推論システム」と呼ばれるものがかなり盛り上がった時代だったのです。
ちなみにいまは、「第3次AIブーム」と呼ばれているようです。
もっとさかのぼれば、AIの研究は1950年代に始まっています(第1次AIブーム)。
いろいろな知識を入力し、答えを出すといったトライアルは、70年ほど前からありましたが、データを処理できるスペックがなく、うまくいきませんでした。
わたしが関わったときはコンピュータが進歩し、かなり使えるようにはなってきたのですが、結果的にその時期のAIはモノにならず、しぼんでしまいました。
日常生活のなかでは例外や矛盾したルールが多く、対応することができなかったことがブームが終息してしまった理由です。
その頃に比べると、現在のAIはとても進歩しているものの、人間がたくさんのデータを入れて、どう推論させるか、という役割を与えられているだけです。
「学習システム」もあるのですが、それも人間が与えているものに過ぎません。
ですから、「ある部分だけ」に限って人の知能に代わることはできても、完全に人間の知能に代われるものではないとわたしはとらえています。
そもそも、「人工知能」という言い方自体、違和感があります。
言葉の定義だけの話なのかもしれませんが、「人工生命」というものができないのと同じで、「人工知能」も本来はあり得ないものです。
人間が、ある条件でデータとプログラミングを与え、推論をさせたり、答えを出させたりしているだけなので、人間の知能とはまったく別物なのです。
わかっている人は多いのかもしれませんが、AIに対する誤解が多いように感じています。
AIがいくら進歩しても、先ほど言った通り、データ量と性能が増えていくだけであって、本質的には変わることはありません。
もちろん、仕事の効率を上げるために使う分にはいいのですが、必要以上に、情報に踊らされなくてもいいのではないでしょうか。
このコラムの参考文献、弊社代表取締役 玉原輝基のAmazon11部門1位の電子書籍『人生は「かけ算」だ!』(BLA出版)のリンクはこちら。
